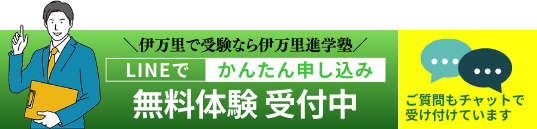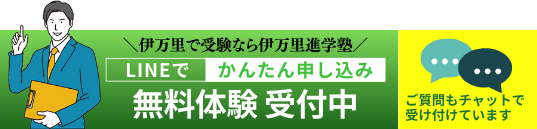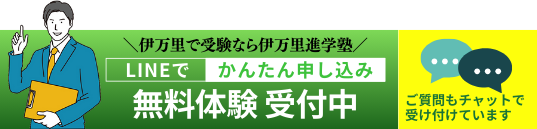夏期講習:数学一学期復習
主な進学先
国公立大学:
佐賀大学(医・医、教、経、理工、農)、九州大学(理、経)、長崎大学(経、工)、長崎県立大学(経営、地域)、北九州市立大学(経、法)、大分大学(教)、熊本大学(法)、宮崎大学(工)、尾道市立大学(経情)、和歌山大学(経)、下関市立大学(経)、山口県立大学(看)、長岡造形大学(美)名桜大学 他
私立大学:
福岡大学(工、経、商)、久留米大学(看、経、法)、西南学院大学(法、国際)、立命館アジア太平洋大学(ア太、国経)、福岡工業大学(工、情工)、九州産業大学(経、国際、観光)、崇城大学(薬、工)
近畿大学(法)、中央(文)明治大学(経営)、日本大学(経)、中村学園大学(教育、栄養)、他

「高校数学の壁」— 中学数学とはまったく違う世界へ
中学から高校へ進学するとき、多くの生徒が「数学の壁」に直面します。中学までは何とかついていけたのに、高校に入ると急に難しくなり、授業についていけなくなる… そう感じる生徒が増えるのです。
だから、伊万里進学塾の生徒は、高校入学前に一学期の中間テスト、速い子は期末テストの範囲までを先取り学習します。
実際、当塾も先取り対策をしないでいたころ(十数年前)は、赤点に近い点数を取ってくる子も多くいました。そこで先取り学習をして、高校の授業で反復、そして塾でもまた反復、そうやって定着させ、80点~100点をとってくるようにしてきました。
では、なぜ高校の数学はそんなに難しいのでしょうか?
① 抽象度が一気に上がる
中学数学は、具体的な計算や図形を扱うことが多かったと思います。しかし、高校数学では「文字を使った一般的な議論」が増え、考え方がより抽象的になります。たとえば、中学では「一次関数」のグラフを描くことが中心でしたが、高校では「一般の関数」を扱い、それらの性質を論理的に分析する必要があります。
② 計算量と手順の増加
中学数学では、一つひとつの計算や公式が比較的シンプルでした。しかし、高校数学では、一つの問題を解くのにいくつものステップが必要になります。例えば、「二次方程式を解く」という単純な操作だったものが、「二次関数の最大・最小を求める」「場合分けをしながら議論する」など、より高度な考え方を要求されるようになります。
③ 理解が追いつかないと、連鎖的に苦手になる
高校数学は積み重ねの科目です。基礎の理解が不十分なまま進むと、新しい単元がどんどんわからなくなります。たとえば、「三角関数」が苦手なままだと、「ベクトル」や「微分・積分」でもつまずく可能性が高くなります。このように、ひとつのつまずきが次の学習内容にも影響を及ぼしやすいのが、高校数学の大きな特徴です。
④ 自学自習では限界がある
高校生になれば、当然自分で勉強する時間も増えます。しかし、数学においては「独学ではなかなか理解しにくい内容」が急増します。特に、問題集の解説を読んでもピンとこない、そもそもどう考えればよいのかわからない、という状況が起こりやすくなります。
だからこそ、高校数学を乗り越えるためには、適切なサポートが必要です。お子さんが「わからないまま放置してしまう」ことを防ぐために、早い段階で「数学の学び方」を身につけることが大切です。
高校生活が始まると、新しい環境や人間関係に慣れることにもエネルギーを使います。その中で、数学が「気づいたら取り返しのつかない状況になっていた」というケースは決して珍しくありません。だからこそ、最初の段階でしっかりと準備し、「高校数学に通用する学習習慣」を身につけることが、お子さんの未来にとって大きな助けになるのです。
高校での数学の学びが、お子さんの可能性を広げるものになるように。今のうちから、その準備を今から始めましょう。
数学Ⅰ一学期復習講座
| 高1生 7月22日㈫~8月23日㈯ | 2時間×8日間 25,300円 |
|---|
日程詳細についてはお問合せ下さい
いかがでしょうか。
このように、高校数学先取り講座なら、学習の習慣化、大学合格に直結する基礎学力養成ができます。
当塾の高校数学先取り講座に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。